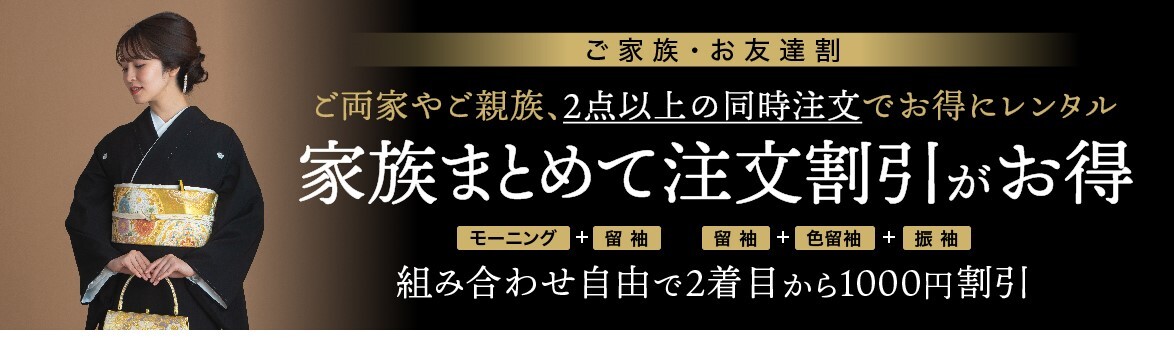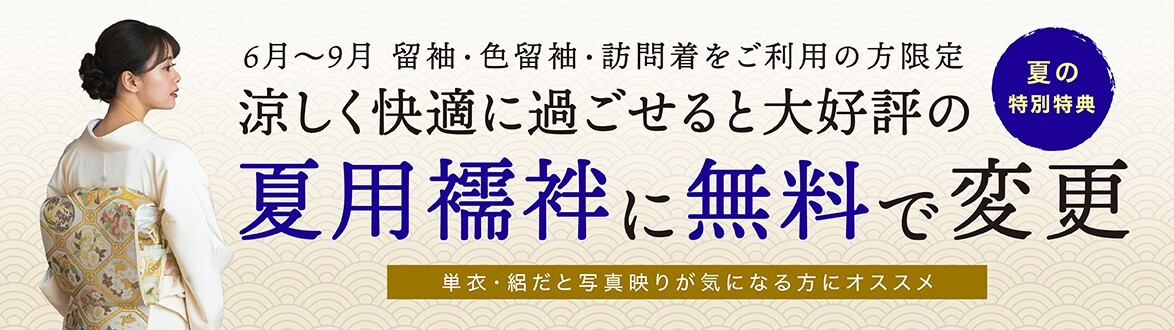振袖にはどんな意味がある?他の着物との違いや絵柄について解説

振袖は女性が成人や結婚など特別な節目を迎える際に着用する日本の伝統的な着物です。その美しい姿で成長や新たなステージへの出発を象徴するとともに、振袖には地域や家族の伝統、華やかさや繊細さなど様々な意味が込められています。今回は、そんな振袖の意味や由来、特徴について詳しく解説します。
振袖とは?
「振袖」と聞けば、華やかな柄の描かれた、袖の長い着物を想像する方が多いでしょう。実際その通りで、振袖は長い袂(たもと)のある袖を付けた着物のことを指します。一般的には大人の未婚女性が着る第一礼装(正礼装)で、同じ格にあたる着物は、既婚女性が着る「黒留袖」、未婚・既婚問わず着用できる「色留袖」と「喪服」です。
現代では、主に20歳になったことを祝う成人式や、結婚式・披露宴に列席する際に着用されることが多く、そのほかに式典や発表会、結納などでも着用されることがあります。
振袖とは本来「若い女性が着る着物」であり、未婚・既婚による制約はありませんでした。
女性の社会進出が目覚ましく、キャリアを持った20代後半〜30代の未婚女性が増えている近年では、比較的幅広い年齢層に、列席衣裳として着用されています。
振袖の特徴とは

振袖は、若い女性のための着物であることから、華やかで若々しい柄が多いのが特徴。衿、胸、肩、袖、腰周りから裾にかけて、着物全体に模様があしらわれているほか、広げると一枚の絵のように柄がつながる「絵羽模様」に仕上げられています。
また、最大の特徴でもある長い袖は、片側が縫い付けられ、片側が開いている「振八つ口(ふりやつくち)」の形になっています。「振八つ口」は「振り」とも呼ばれ、浴衣や羽織、長襦袢など女性用の着物には全般にありますが、男性の着物にはありません。この「振八つ口」がとても長い着物が振袖ということになります。
振袖の原型は飛鳥時代に出現
振袖の歴史はかなり古く、飛鳥時代にはすでに原型となる着物があったとされています。さらに、そのルーツを紐解いていくと、縄文時代の「貫頭衣(かんとうい)」と呼ばれる着物にまで辿り着くというから驚きです。
元来、振袖は若い女性や、元服(成人)前の男の子が着用しており、男子は17歳、女子は19歳になると、袖を短くして「振八つ口」を縫うのが習わしだったといわれています。
現在に近い形に落ち着いたのは江戸時代。さらに明治以降に入って、未婚女性の第一礼装として定着しました。
なぜ成人式に振袖を着るの?

振袖といえば成人式の晴れ着のイメージがありますが、では、なぜ成人式に振袖を着るのでしょうか? その理由は大きく分けて二つあります。
ひとつめは、未婚女性の第一礼装が振袖だから、というシンプルな答えです。
成人式は日本の冠婚葬祭でいえば「冠にあたり、第一礼装が求められる式典の一つです。そのため、男女を問わず日本の伝統衣裳を着用する方が多く、和装で出席すること自体が人生の通過儀礼の一つと考えられています。
ちなみに、いまでも成人式に洋装ではなく和装が選ばれる理由としては、普段は着用する機会の少ない華やかで伝統的な衣裳で臨むことで、成人という節目を迎えたことをしっかりと自覚できる。そのことを意義深いと考える方が多いようです。
もうひとつ、振袖には「厄払い」の意味もあります。着ることによって厄を払って身を清め、その後の人生が幸せなものとなるように、という親の願いが込められた衣裳ともいえます。
振袖の種類と着用シーン

江戸時代の振袖は「小袖」と呼ばれ、初めの頃は55cm〜95cmほどしかありませんでした。袖が長くなっていった理由は、「踊り子たちが袖を振ることで感情を表現した」「袖が長いと所作が美しく見える」、また「袖を振るという動作で厄払いやお清めができる」と考えられていたことから、よりたくさんの厄を払えるように袖が長くなった、など諸説があります。
江戸時代末期には振袖は95cmから、長いものでは122cmもあったといわれています。
現在、最も袖の長い振袖で114cmほどの長さがあります。また、袖の長さによって、大振袖、中振袖、小振袖の3種類に分類され、袖が長いほど、格が高いとされます。
大振袖
一番袖が長い大振袖の袖丈は約114cmほど。地面につくほどではありませんが、大抵の場合、着る方のくるぶしくらいまでの長さがあります。振袖の中でも最も格式が高く、婚礼衣裳としても着用されます。花嫁が着用する場合は、裾に綿を入れ、引きずるように着付けを行うことが多く、その場合は「引き振袖」「お引きずり」などと呼ばれます。
最近では、身長の高い方が増えていますが、160cmよりも低い方であれば、身長に合わせて引きずらない程度の袖丈に調整することも。160cm以上の方の場合は、袖丈を伸ばす必要はありません。
大振袖の一般的な着用シーンは、成人式はもちろん、結婚式のお呼ばれ衣裳、特に親族として出席するケースなど、よりフォーマルなお祝いの場で着用されます。以前は、留袖と同様に背中と両胸、両肩に5つの紋を入れる「五つ紋」が正式とされていましたが、振袖は紋の数で格が上下する事はないので、最近では華やかな絵羽模様を優先し、紋を省略するのが主流となっています。
中振袖
かつて成人式といえば大振袖が主流でしたが、最近、成人式で人気になりつつあるのが、中振袖です。袖丈は約100㎝、身長にもよりますが、足首よりも上になることが多いでしょう。格は大振袖の次に高く、着用シーンは成人式のほか、結婚式のお呼ばれ衣裳や、お見合いや結納など、着用されます。
お呼ばれの結婚式で着用する場合は、主賓の方よりも格が高くなる事は避けたいので、中振袖を選ぶのがベター。また、花嫁がお色直しなどで振袖を着るのがわかっている場合は、色などかぶらないように注意しましょう。
着る人の身長によっても袖の長さは見え方が変わります。大振袖・中振袖という種類にとらわれすぎず、着る方に合わせたバランス感で選ぶことをおすすめします。
成人式の振袖は、着ることになる新成人の方が主役。袖の長さはもちろん、柄や色など、着る方のお好みを優先しながら選んでみてください。
小振袖
振袖の中で一番格が低いのが小振袖です。
袖丈は約85cmで動きやすく、卒業式に袴と合わせて着用されることが多い着物です。大振袖や中振袖を袴に合わせると、やや袖が長すぎる印象になりますが、小振袖ならバランス良くまとまります。
小振袖はセミフォーマルにも対応が可能なので、パーティやカジュアルな観劇・お茶会など、お出かけ着としても、堅苦しくなりすぎず着用することができるでしょう。
振袖の柄の意味とは

着物の柄はさまざまな意味や願いが込められたもので、着ていく場所に合わせて、思いに沿った柄を選ぶのも楽しいものです。
振袖には、長寿や平和、繁栄などを意味する縁起の良い柄が描かれています。今回は、その中でも代表的な「吉祥文様」と「有職文様」の二種類についてご紹介します。
吉祥文様
「吉祥文様」は、着物やさまざまな伝統工芸品にあしらわれてきた、特に縁起の良い柄として知られる柄です。大陸から伝わってきたものが多く、古代の中国で縁起が良いとされていたモチーフが色濃く反映されています。
繁栄や長寿の意味を込めた柄は、お祝い事に関わる衣裳や品物はもちろん、日用品にも広く描かれてきました。
代表的なところでは、長寿の象徴である亀の甲羅をモチーフにした「亀甲」(きっこう)、未来永劫の平安を願う「青海波(せいがいは)」、家の繁栄や長寿を願う「沙耶型(さやがた)」、五穀豊穣のほか、子孫繁栄の願いも込めた「入り子菱(こびし)」など。最近人気の「麻の葉」は、魔除けの意味が込められた柄です。
有職文様
吉祥文様が大陸から伝わった後、平安時代に入って遣唐使が廃止され、日本独自の「有識文様」が、平安貴族の中で流行しました。十二単や束帯のほか、調度品などにも多く描かれた、優美な織り文様です。
当時、宮中の儀式や行事に関する研究者や学者(有識者)たちが着用することが多かったことから「有職文様」と呼ばれるようになったといわれています。
水蒸気が立ち上る様子を描いたといわれ、“運気を上げる柄”として有名なのが「立涌(たてわく)」。瑞雲や波、藤などと組み合わせて描かれることも多く、それぞれ「雲立涌」「波立涌」「藤立涌」と名前がついています。
また、丸いフォルムから円満を表す「七宝」は、宝尽くしを構成する柄の1つになっています。
まとめ
ひときわ華やかな「振袖」は、着物のなかでも未婚の若い女性に限られ、なかなか着用する機会を得るのも難しいですから、成人式は振袖を着られる貴重なチャンスです。さまざまな色柄が豊富にそろい、着る方の好みの色や柄を選ぶ楽しみもひとしおでしょう。ぜひ、描かれた柄の意味も知って、お祝いの気持ちや願いなどを込めて、お気に入りの一着を選んでみてください。